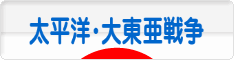立花隆批判 「天皇と東大」を読む 14
立花隆 「天皇と東大」文春文庫版 第4巻「大日本帝国の死と再生」は、基本的に戦争直前の東京大学経済学部の内部状況に光をあてて、どの学閥グループが戦争体制に迎合してどの学閥グループが戦争に反対し、学内の地位が低下したり、あるいは教授の地位を追われたかを記述している。
この見方には、大きな欠点がある。
戦争体制そのものは、正義の戦争をする場合には、否定するほうが間違いなのであるから、戦争体制に迎合は、見方によっては、戦争体制に果敢に協力、とも言えるからである。
こういうと、戦争に正義の戦争なんてない、という人もいるだろう。
ならば、イラクに本当に、大量破壊兵器があった場合はどうなのか。
また、あっても、アメリカのイラク戦争は侵略なのか。
これでも、ピンと来ないならば、もっと簡単明瞭な事例をあげよう。
北朝鮮の侵攻を受けた韓国は、戦争を否定して、平和を維持するために、抵抗せず、すぐさま、白旗をあげて、降伏して、半島全体が金日成一党独裁政権になればよかったのだろうか。
ソ連から見たアメリカ憎悪、アメリカをつぶしてやりたい意思を日本に代行させる狙いを代行する林房雄の「大東亜戦争肯定論」は、けっして日本の侵略ではなく、英米の東亜侵略に対する抵抗なのだ、という戦争の正当性、理由を表明したものである。
これに対しても、戦争にどんな理由もいらない、すべての戦争は悪で、戦争で被害を被るのは庶民だ、というなら、北朝鮮に対する韓国の抵抗も、黙って降伏すればよかったという論理にならざるをえない。
この絶対平和の論理では、武力侵攻したほうを常に平和勢力は応援せざるを得なくなるのである。なぜなら、先に侵攻したほうが悪だからといって、反撃すれば、戦闘は激化するから、結局は絶対平和の論理は先に侵攻した側を非難したとたんに、口先だけの批判か、それとも、武力反抗するしかなくなるからだ。
こういった考察を抜きにして、立花隆は、「リベラルな理想主義者の集まりであったはずの河合派があっというまに、空中分解して戦争体制支援者の集まりになってしまったのである。」と書く。
「天皇と東大」 文春文庫 第4巻 89ページ
しかし、「リベラルな理想主義者」は絶対、戦争に反対すると決まったものだろうか。
なぜなら、中国、ソ連、アメリカは、日本とドイツに対する戦争を、「反ファシズム戦争」という正義だと主張している。これは、リベラルな理想主義がファシズムにあらがったという意味だろう。
それとも、戦後の日本の平和主義者は、中国共産党の反ファシズム戦争、勝利記念の主張に少しでも、「いや、戦争に正義の戦争なんてないから、祝ってもらっては困る」とちょっとでも思ったろうか。
日本人が戦争やむなしという理由を述べれば、戦争に正義の戦争はないと言って、効く耳をもたず、他国が日本と戦争をした理由には、もっともな理由だ、悪い日本をつぶしてくれてありがとう、というのはおかしくないか。
日本の場合には、まともな理由などあるはずがない、と考えて非難し、蒋介石の軍閥との戦争、国民党と共産党の戦闘はなんとも思わないのが、日本の平和主義者である。
姜尚中は、日本の高度成長の出発は朝鮮戦争特需からだったというのだが、韓国の抵抗戦争に参加した国連軍に対して、日本の企業が物資を売ることによって、提供するのを日本政府が禁じたならば、韓国民衆はめでたく、北側の勢力に完全支配されて、南側中心に餓死の多発する国柄になっていただろう。
姜尚中は、餓死と政治犯収容所と公開処刑に国になってもいいから統一してほしかったらしい。
もちろん、戦争に正義は一切ないから、どんな全体主義体制国家を構築する党集団が、解放と称して、侵攻してきても、「戦争をエスカレートさせない」ために、すぐさま降伏するという選択はありうる。
その場合、まさに憲法9条2項はこの抵抗なき服従にピタリと整合しており、抵抗しないのだから、武器は一切いらないことになる。
しかし、中国はけっしてそうは考えないからこそ、「反ファシズム戦争の対日勝利」を祝うのではないか。中国が絶対平和主義者なら、戦勝なるものを祝う事はしないだろう。
ましてや、日本と戦争したことのないのに、勝ったと祝っているくらいなのだ。
そしてアメリカはアメリカで、戦争突入に際してプロパガンダ映画を作っては戦争に消極的な国民のやる気を起こさせ、日系人を収容所に入れて閉じ込めるという戦時の不正義を行使していた。おそらく、何の不正もなさずに、正義の戦争を貫く国家もおそらくあるまい。ソ連もドイツとのファシズム戦争との過程で、ポーランドの半分を占領して、ポーランドの将来の発展を抑制するために、ポーランド人将校を計画的に大量殺害した。
このように、どの国も、戦争では不正をしているというなら、やはり戦争はいけない、というわけで、侵略者には、抵抗するな、ということになるのだろうか。
このような問題を解きほぐす面倒な作業をはぶいて、簡単に「積極的平和主義」と言ってしまうのは、キセル(区間と区間の真ん中を抜いて乗車切符を不正に安くあげる)だろう。
立花隆は「天皇と東大」文春文庫版 第4巻104ページに次のように書いている。
「昭和12年に日華事変が開始されると、日本の社会全体が戦時体制に入っていった。
開戦と同時に開始された国民精神総動員運動と翌昭和13年の国家総動員法の成立によって、日本の社会はすみずみまで戦時体制そのものになっていった。」
だが、これ自体、なんの異常な事態とも言えない。というのは、第一次大戦の欧州の戦争が国家総力戦の始まりであり、中国国民党を支援しているのが、時にソ連、時にドイツ、最終的には、満州への領有意欲を持つ漢民族の国民党に英米が支援しての広大な領土を持つ中国との戦争が容易にかたずきそうにないのだから、総動員体制を取るのは何の異常性もあるまい。
問題は総動員体制でhなく、そもそも、シナとの抗戦を泥沼化すべきでないのに、泥沼化させた事が問われねばならないのに、立花隆は、国家総動員体制が問題だという。
国家総動員体制は結果であって、問題は満州よりも、南へ南へ踏み込むことが、英米という当時の日本にとってあまりに巨大な敵との直接対決になぜ、踏み込んでいったのか、という批判的な検討だろう。戦時体制に入ったことが問題ではなく、この時のを先に、日本から、反ソの問題意識が遠のいて、反米一色になり、同時に、巨大な相手でも神国だから、なんとかなるというカルト信仰が普及されつつ、シナ大陸に歩を進めて行ったのということこそ、時代の実相なのである。
ここで改めてはっきりさせておきたいが、立花隆は15年戦争観、すなえち満州事変から日英米戦争敗戦までを一連の流れとみている。
つまり、満州事変はソ連向け、日華事変前半は満州を意識するが、次第に近衛がセッティングした平泉澄きよしのイデオロギー注入によって次第に英米戦決意へ変化していき、独ソ戦で、日本のソ連無視、英米戦決意が固まった、という様相がまったく見えていないと言っていい。