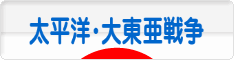立花隆批判 「天皇と東大」を読む 11
平泉澄きよしの言う「敵は英米」と「皇国」の合体した主張は、日本の①共産党転向組、②非日本共産党のマルクス主義者、③日本権力中枢に食い込んだマルクス主義者たちにとって非常に都合のよい主張だったことは間違いない。
なぜなら、当時、世界中のマルクス主義者の常識は、独占資本主義の帝国主義国家体制を革命するに、平和を維持しつつ権力を移行できるなどと予想するほうがキチガイじみた妄想とみなされ、暴動、内乱による革命は必至と考えられていたが、その一つの道筋として、あまりにも当然に、対外戦争とそれに伴う国民の犠牲の結果、国民が現行支配勢力に対して強烈な不信と憎悪の念を向けるということが想定されたからである。
皇国思想が極大化すればするほど欧米近代思想から異様で偏狭な個人を圧殺する解体すべき悪習として映り、敗戦時には弾劾されようし、なによりかにより、欧米列強の圧倒的国力に精神主義で立ち向えば立ち向うほど、国民の被害は大きくなり、すさまじいばかりの傷を受けた民衆はどんなプロパガンダも必要がないほど、民衆自らの怒りによって、天皇と財閥・大企業支配層を打ち倒しにかかるだろう。
このような意味で、平泉澄きよしの存在は極左革命構想を腹に一物する者たちには、非常に好都合なものだった。平泉澄きよし自身が稀代の道化だったのか、天才的な皇室破壊の策士だったのか、謎である。
念のために繰り返すが、平泉澄きよしはなぜか、国史学者であるにもかかわらず、フランス革命、すなわち、王族をギロチンで処刑した過程を研究している。また、平泉澄きよしの直弟子田中卓は、女系天皇肯定論者である。だから、平泉澄きよしが単に、狂信的域に達した皇室尊崇理論家だったのではなく、案外、平泉澄きよし本人がルソー的な人民主権論による革命の引き金を意図して引こうとしていた可能性も考慮しないわけにいかない部分がある。
立花隆は平泉澄きよしについて「日本は天皇の国、神の国だから、日本軍は向かうところ、敵無しで、当然連戦連勝と思っていた」と簡単に言う。
が、本当にそうなのだろうか。
西部邁が回想する西部邁の父親をはじめ、実のところ、庶民レベルで多少とも思慮深い、またアメリカの産業技術の状態を新聞記事の端々から総合的に判断して、英米とまともに戦争して勝利できるはずがない、と考えていた人々は珍しいわけではない。
ただ国史と神道に専念していたわけではなく、ドイツのリッケルト、クローチェなどの歴史学者に会ったり、パリに行ってフランス革命を学ぶほどの知性のある平泉澄きよしが、果たして「日本は天皇の国、神の国だから、日本軍は向かうところ、敵無しで、当然連戦連勝と思っていた」のかどうか、怪しいというしかない。それとも、本当に東大国史科首席卒業の平泉澄きよしがそれほど、一面、阿呆でもあったのだろうか。
戦後日本の極限まで通俗化した共産党のイメージである「平和を求める共産党」の立場からすれば、平泉澄は立花隆が指摘するような「戦争を悪化させた張本人」として日本歴史上けっして忘れてはならない労働者、貧困大衆の敵だということになる。
しかし、元々、共産主義が「平和の党」という事自体が、まるっきりのプロパガンダなのである。
なぜなら、共産主義が敵としているのは、共産主義の実現していない現体制が資本主義体制で、独占資本主義、国際金融資本によって、労働者を抑圧している、そういう体制であるが、「平和」が大事というなら、そういう体制が「平和に持続する」ことを意味するではないか。
ここまで、言ってしまうと、いかに庶民でも、あれ?確かに。なんだか変だぞ、と思うだろうから、決してこの矛盾がばれないよう、ばれないように、憲法9条が平和を守ってきたのです。平和こそ大事です、という。
では、なぜ、共産主義者は、民衆に向けては「平和こそ大事」と言って、イエスキリストのように、革命を呼びかけはしないのだろうか。
① 日本の経済成長の中で予想以上に合法野党としての国政から市町村議会までの職業政治家としての生業が個人的に豊かで安楽な暮らしを保証してくれることに味をしめて、庶民のいやがる生臭い騒乱のイメージをひたかくしに隠すようになった。
② 国政、地方自治体議会に席を占めて、公費で生活する安楽性を維持するために、与党として国政運営、自治体の行政運営を担う能力は本当のところ、ないので、選挙民に「平和」と「富の再配分」「政治家の不正の番人」の役割を認めてもらうことによって、反体制家業を維持するようになった。
③ 当初は、社会主義国が資本主義国の経済恐慌を免れて安定成長を遂げた末に、経済崩壊した資本主義国において、怒りをもって立ち上がった日本国民貧困大衆の暴動、騒乱をソ連や中国共産党人民解放軍が支援してくれる状況を夢みて、日本の軍事力をなんとか、抑えようと抑えようと、真剣に努力してきたが、そのうち、ソ連も中国もその他の共産主義諸国もなんら革命の先行者でもなんでもない茶番なのではないか、という疑念がじわじわとせり上がってきたが、引っ込みがつかなくなって、人権、フェミニズム、アメリカの格差、侵略戦争批判、国際金融資本の世界支配と言った知的抵抗に活路を見いだすようになった。
立花隆「天皇と東大」からの孫引きだが、マルクス主義歴史学者の色川大吉は「ある昭和史」に「私(色川)は東京帝大の国史科に入ってからも、主任教授平泉澄の弟子から、「日本海軍の首脳たちが親英米派、和平派で困っているのだ」という文句を聞いたことがある」
と書いているという。
韓国、中国共産党および日本共産党の日本現代史観は、「日本は日清日露戦争と一貫して侵略戦争を続けてきた」と解釈している。
アメリカの左翼もまた、そうなのだが、アメリカの保守の場合は、義和団の乱で日本と同盟関係にあったこと、日露戦争では、日本に資金協力をしたことから、日清日露を日本の悪の発露とは見ない。保守の半分は日中戦争は日本のソ連の脅威からの自存自衛、そして太平洋戦争はルーズベルトにも落ち度があると見ている。そして保守のそのまた半分は、日本は経済恐慌の末に、ドイツナチズム同様、天皇制ファシズムに落ち込んで見境も無い軍国主義に突入して行ったから、やむを得ず原爆を使用して日本軍国主義の本土決戦思想を断ち切るしかなかった、と考えている。
そして日本の青少年は、日清日露戦争の意味がよくわからないと言ったところだろう。
アメリカの保守の半分ほどが、真相に近い解釈をしているのである。
色川大吉の言う当時の海軍首脳の英米和平派の真意は、ワシントン条約を典型に、少なくとも話し合いが可能な相手が米英だったと言うこと。そして、なによりも、いざ本当に相手とするには、あまりに手強い相手で、不利な講和しか見込めないような巨大過ぎる相手が、英米であり、しかも、英国の権益を日本がまともに否定すれば、米国も出てくるという判断が海軍首脳の基本認識だったからである。
これは、基本的に満州事変の当事者石原莞爾も同様の見方をしており、「世界最終戦争は日米戦争とは思っても、それは石原の生きているうちに実現しないような先の話で、石原の寿命のあるうちにやるようでは、必ず敗北する馬鹿げた戦略にしかならないと考えられていたから、石原は北支に向かう陸軍首脳と対立するようになっていった。
戦後日本のマスコミ人士、TBS、テレ朝、NHK、朝日新聞、毎日新聞、岩波書店の編集者、記者、ディレクターらが、半知識人としての自己の職業上の政治スタンスを決めるにあたって、援用したのが、
①日本共産党による「明治の富国強兵政策以来のアメリカ帝国主義への反発憎悪を隠しつつのアジア侵略。(林房雄)」
②司馬史観。民社党史観。すなわち、日露戦争の勝利におごりたかぶって、狂気が蔓延した軍国主義によって中国を侵略し、これを民主主義国家アメリカの制裁を受けた、とする。
③アメリカリベラルによる見方。日露戦争までは、自存自衛だったが、アジアの盟主になった日本は天皇制という伝統をカルト化して、アジア全体を天皇の領土にしようという狂った軍国主義ファシズムに陥った。本土決戦思想を持って、日本国民と米国兵士の犠牲を増やような戦略を日本は取ったので、原子爆弾で、これを一気につぶすほかなかった、とするもの。
④丸山真男学派による天皇制ファシズムと天皇の戦争責任を問うことが日本が本物の民主主義になるのに必要、というもの。
これらの認識をごちゃまぜにつまみぐいしたものが、NHKをはじめ、日本の戦後マスコミの国民に提供した平和思想の元ネタである。