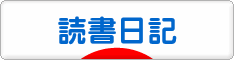大西巨人 小説 「縹富士」
「縹富士」はなだふじ
これはといった言葉つかい
旧年極月きゅうねんごくげつ
去年の12月・・・の事をそう書いている。
この作者は、報道された、と書きがちのところを報道せられた、と書く。
担当をあてがわれたは、充て行われた、と表記している。
一昨昨年さきおととし
旧臘きゅうろう
とは、享年の12月という意味である。
大西巨人という作家はちょっと不思議な発想がある人で、筆者本人に近い登場人物を出しておいて、編集者という設定の青年が、担当の作家と話していて、「目から鱗が落ちる思ちた」ように啓発されて、と書く。
これは非常に変わっている。通常は筆者に近い人物の話を聞いた青年が、「目から鱗が落ちた」ように、とは書かない。なんだか、自画自賛しているみたいだからだ。
大西本人と目される作中の作家は、現代の主要な文芸小説について、「なんでこんなものを書くのか、わからない」と思っているが、黒澤明「夢」を見た感想は、「なんでこんなものを作るのか、わかりすぎてつまらない」だった。
それとは別に作中の作家が、黒澤明「夢」の第4話「トンネル」の「軍隊敬礼の場面」の敬礼が実際の敬礼とは違う、というのである。
江戸時代の武士が土下座をして大名行列を見送る場面があれば、滑稽だというのと同じくらい滑稽だという。
脚本家・演出家の無知ないし・粗雑
作中作家は、郵便物の署名中の名前の誤記、たとえば大西巨人の巨を「臣」と間違える類の間違いに、特に不愉快を覚える。
この作家は広野という中学生に廣野さんへと返事を書いたところ、広野君は、僕は廣野じゃない、広野だと腹をたてる。なんだ、人の誤字を指摘して、自分もまちがっているじゃないか、と。
富士山のひときわ高くぬきんでた は、抽んでた、と表記され、ぬきんでたと読む。
日本のある世代、特に大西の世代は、「空襲でか戦場でかさだかではないが、毎日毎日死をひかえて生きていたのだったことを、その作家は、小川洋子の「完璧な病室」冒頭「そして弟が信じられないくらいの若さで、死んでしまったからだと思う。誰だって、二十一の青年の死を容易に想像することなんてできないだろう。二十一といえば、人間が一番死と無関係でいられる時だ」という一節を読んで、ある感慨にふける。
八十歳近くになって、この老作家は、死亡時二十代半ばのある女性の死を知った時の心境を思い出したのである。
この作家は、マルクスの思想にある種の価値を見いだしているのだが、ソ連崩壊の新聞記事を読んでも何の感慨も起きなかったことになっている。
そして、この誤字脱字だの礼儀だの、粗雑を排したりが、案外、左翼だの右翼だの以前に大事なのじゃないかという事を言いたいのだろうな、とうかがわれる事を時々漏らしている
ところで、大西巨人は、ソ連に何の信頼、希望も置かなかったが、和田春樹は、ソ連崩壊後も、未練たらしく、ソ連はそれでも、いくつかの大事なことを成し遂げた、と発言している。大西はだいぶ早くからソ連に信をおかない、マルクス主義の「陣営」からも離れてなお、マルクスの言葉のはしばしを覚えてかみしめている人だった。